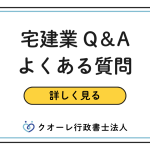【宅建業】略歴書に「虚偽内容」を記載するとどうなる?
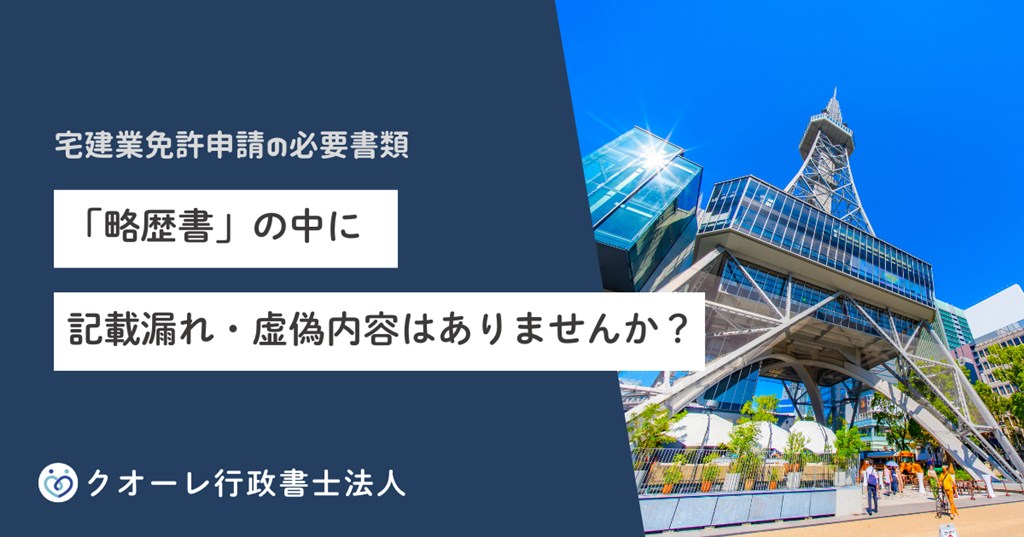
宅建業免許申請の審査に大事な書類の一つでもある「略歴書」。
これはただの「履歴書」のようなものではありません。当事務所で代理申請していた案件でも行政庁から略歴書の内容について詳しく聞かれたことが多々あります。そのため、申請書作成時、各対象者の略歴書の確認作業は慎重に行っているほど、略歴書の内容というものは審査に大きな影響を与えるものです。
このページでは宅建業免許申請における略歴書の記載内容・記入時の注意事項などについて詳しくお伝えしたいと思います。
宅建業免許申請に必要な「略歴書」とは?
宅建業免許申請時に必要書類として、代表取締役・取締役・その他役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士の「略歴書」が提出が求められております。
この書類は単に今までの「履歴・経歴」を記載し、確認するだけの書類に見えるかもしれないですが、実は申請者(法人・個人)だけでなく、重要な役職の方の詳細まで総合的に審査するためのものでもあります。そのため、記入する際に注意していただきたい点もたくさんあります。
略歴書に記載すべき内容
- 氏名・住所・生年月日
- 宅建業における職名
(例:代表取締役、取締役、専任の宅地建物取引士など…) - 宅建士登録番号
- 電話番号(宅建士のみ)
- 職歴(無職期間含む)
- 記載年月日・記名
氏名(漢字・ふりがな)
外国人の場合、通称名の記載でも問題ありません。その際は、通称名が登記されていないことの証明と住民票に記載されていなければなりません。対象書類を取得される際は必ずご確認ください。
宅建士の場合は、略歴書上の氏名と宅建士証の氏名が一致していなければなりません。結婚して氏が変わった場合、宅建士証の変更登録をしていない時は個別ご相談くださいませ。
住所
現在、住んでいる(住民票上の)住所をご記入ください。
住民票住所とは異なる場所に生活の本拠があるときは、2段書きで居住地(居所)を記入しなければなりません。その際は「居所証明」が必要となります。居所証明ができるものとして、「公共料金の請求書(本人氏名と居所)」、「郵便物の写し(消印あり)」などがあります。
職歴
最終学歴終了後から現在までの就職先会社名・勤務内容(事務職/営業など)・役職名(代表取締役・取締役・監査役・専任の宅建士など…)を記載します。この内容が一番詳しく確認され、その内容をもとに審査されますので、漏れのないようにきちんと記入しましょう。
職歴の詳細内容について
- 職歴は「省略なし」で
- 無職期間がある場合も書く(1年以上)※免許行政庁による
- 勤務内容は「宅建業に従事した場合のみ」※愛知県の場合
- 役員の場合は常勤・非常勤も記載
例えば、会社員を辞めて、個人事業主開業し、仕事をしていた場合、その期間も記載しなければならないのですが、その際は「屋号」があったのか、仕事/業務内容の詳細を求められます。また、役員の場合ですが、就退任日も正確に記載しなければなりませんので、就任していた法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を確認し、しっかりチェックしておいてください。
事実と異なる略歴を記載した場合は?
免許拒否になる可能性がある
免許を受けようとする者が宅地建物取引業法第5条第1項に規定する欠格要件に該当する場合、又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合は免許拒否を行います。
宅建協会・全日本不動産協会への加入が拒否される可能性がある
宅建協会や不動産協会は免許行政庁とは別の審査を行っており、該当団体の特別なルートでさまざまな情報を調べます。略歴書に記載すべき事項を「記載しない」もしくは「虚偽内容で記載する」ことがバレてしまうと各協会への入会が断られ、営業保証金1,000万円を供託する必要があります。免許行政庁の審査が通り、免許が下りたとしても協会への加入が断られ、供託する資金がなければ、そのまま廃業する形になる可能性もあります。
記載時の注意事項
役員の場合
就任日・辞任および退任日は正しいですか?
今までの経歴で複数法人にて役員を務めた場合は、各就任日と退任日を登記事項証明書にてしっかり確認してください。
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に登記されていますか?
勤めていた法人で「専務取締役」や「常務取締役」で業務を行っていたとしても、法人内の呼び名である「役職」と登記簿上の「役職」が一致しているとは限りません。宅建免許申請上の役員とは対象法人の「登記事項証明書」に登記されている者を指します。取締役のつもりで業務を行っていたとしても実は登記されていなかったりすることがあります。十分ご注意ください。
政令使用人の場合
他法人の代表取締役になっていませんか?
政令使用人の場合は、「常勤性」を証明する必要があります。代表取締役が常勤できないため、その代わりに常勤するものとして置くのが「政令使用人」であります。しかし、その政令使用人の方で他の法人の代表取締役になっている方が稀にいらっしゃいます。その際は、他法人の非常勤性を証明するとともに、他法人の業務を担わせる者を決めとかなければなりません。そうでなければ、政令使用人にはなれないため、別の人を政令使用人として置く必要があります。
複数法人の代表取締役になっていませんか?
上記と関連することで、政令使用人がいくつも法人を持っていて、かつ、代表取締役の場合はどちらも非常勤性を証明するために該当法人の業務全般を担う常勤者を立てる必要があります。常勤者は「アルバイト」、「パートタイマー」では立てることができませんので、ご注意ください。
専任の宅建士の場合
他社で専任の宅建士として働いたことはありませんか?
宅建士の略歴書で一番間違えやすい部分です。他社で専任の宅建士として働いたことがあれば、その従事先の追加や退職に伴う従事先の変更等をしっかりしていたかを確認してください。
そして、不動産会社で勤めていた際に「専任」または「一般」であったか把握しておく必要があります。
その他にあることとしては、「極端に短い期間(1ヶ月未満)」しか不動産会社に勤めていないとしても必ず記載してください。
空白期間の記載漏れはありませんか?
前の会社を退職してから転職するまでの空白期間(1年以上)は必ず記載してください。愛知県の場合は、1年以上ですが、他の都道府県の免許行政庁によって基準が異なりますので個別に確認する必要があります。
宅建業免許申請を行政書士に依頼するメリット
- 法律に基づく正確な「申請要件」のチェックが可能
- 各都道府県の基準に合わせた申請書作成
- 面倒な書類収集をまるごと依頼できる
- 宅建協会・保証協会への入会申請もワンストップでできる
- 免許取得後の忘れがちな変更届出・更新手続きをサポート
宅建業免許申請は「申請要件」のチェックから必要書類の収集、申請書の作成、各協会への入会手続きなど複雑な部分があります。新法人を設立して、ぼんやりと「宅建業をやりたい」と思っていても「いざ、何からやればいいの?」にぶち当たります。そもそも宅建業を行う名目で法人を設立するのであれば、設立時に宅建業のための目的欄の設定などが必要です。また、事務所要件、宅建士や代表取締役の常勤性など申請要件をクリアする必要があります。その要件をクリアできなければ、免許申請はできません。
「宅建業を行うために事務所を借りたけど、まだ開業できていない」、「複数法人が同居している事務所だと開業できるの?」などたくさん悩みや質問をいただいております。
そこで、行政書士はお客様の法人設立、宅建業免許申請における申請要件のチェックなどを行い、必要書類収集から申請書作成まで総合的にサポートすることで、無駄なくスムーズに宅建業免許を取得できるようにお手伝いできます。クオーレ行政書士法人はあらゆる行政手続きに対するお客様の悩みを解決できる「痒いところに手が届く行政書士」、「かかりつけ行政書士」を目指しています。